こんな時、
どうしたらいいの?
こころの悩みQ&A
作成日:2025.05.09

医療機関の受診に
関するお悩み
親しくしていたご友人と最近関係がうまくいかなくなって、モヤモヤしたり不安になったりしていらっしゃるのですね。人間関係の悩みは、時に眠れないほどのストレスになりますよね。不安を感じたり、イライラしたりしてしまうことは、日常的に誰しもが経験されることと思いますが、時間が経つと自然と解消されていることもあります。
ただ、なかなか寝付けない日が続いたり、数週間にわたって意欲が低下してしまったりする場合には、医療機関を受診することもお勧めします。きっかけは些細なことであっても、日頃のストレスも、ちりも積もれば山となることがあります。どのような悩みであっても、一度、専門家に相談してみると、解決の糸口が見つかるかもしれません。
回答者は、
心理士の野口恭子先生です。

野口 恭子(のぐち きょうこ)先生
医療法人和楽会
心療内科・神経科 赤坂クリニック
「このまま消えていなくなりたい」と思っているのは、相当に追い詰められている状態なのではないかと思います。これまでの人生で、あなたなりに対処してきたなかで、うまくいかないことが重なったり、周囲からも見捨てられたような感じがあり、自分ひとりで抱えざるを得なかったり、たいへん苦しい状態が続いているのではないかと思います。八方ふさがりの状況では、一般的に、何かを改善したいという気持ちを持てなくなってしまうことが多いです。
そのような状態のなかで「医療機関」という選択肢が浮かんでいること自体が、とても大切なことです。特に、「このまま消えていなくなりたい」という気持ちは、「希死念慮(きしねんりょ)」という症状である可能性が考えられます。この症状の影響を受けることで、自分の意思に関係なく死に駆り立てられてしまうこともあります。深刻な状態であり、治療や支援を受けることが現状の改善に役立つ可能性があります。
医療機関(精神科)では、「こころの不調」に関する専門的な視点で現在の状態を整理し、あなたの状態に合わせて、さまざまな治療や支援を提供しています。現在の状態に「こころの病気」の診断がつく可能性も考えられます。診断は、適切な治療や支援につながる道標にもなりますし、客観的に自分の状態を把握することを助けてくれるものでもあります。
これまでのあなたの事情を考えると、医療機関への受診はとてもエネルギーが必要な一歩であると思います。「わかってもらえなかったらどうしよう」「話しても意味がないと思う」「もうこれ以上傷つきたくない」「アドバイスされても、できなかったらどうしよう」という気持ちもあるかもしれません。医療機関では、患者さんはそのような事情や気持ちがありながらも、一歩を踏み出して受診されていると理解しています。そのため、安心して受診していただければと思います。
回答者は、
心理士の広瀬慎一先生です。
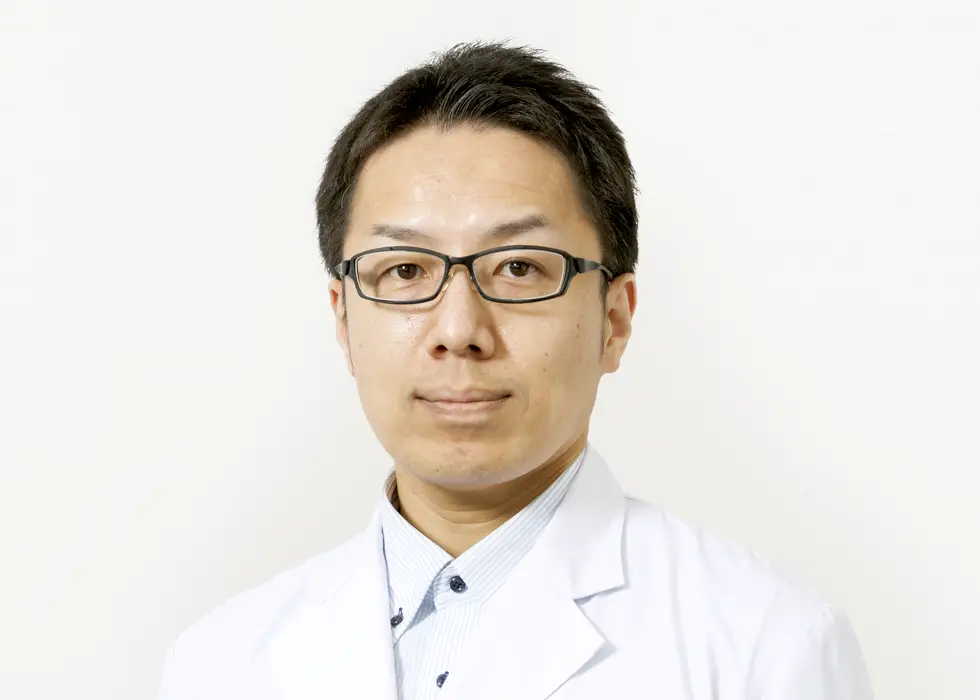
広瀬 慎一(ひろせ しんいち)先生
医療法人社団 五稜会病院
ご主人のご様子、心配ですね。不眠やだるさ、気分の落ち込みというご様子から、うつ病などのこころの病気が関係しているかもしれません。うつ病や不安症などのこころの病気を専門に診るのが「精神科」で、こころの悩みが関係する身体の病気を専門に診るのは「心療内科」ですので、精神科・心療内科を標榜している病院やクリニックを受診してみるとよいかもしれません。
でも、もしご本人やご家族にとって、精神科や心療内科はハードルが高く感じられるようでしたら、まずはかかりつけ医や地域の保健所などの公的機関の相談窓口に問い合わせてみると、適切な病院を紹介してくれることもありますので、相談してみてください。ご家族が説得するより、第三者からお話ししてもらった方が、ご本人も受診のきっかけになるかもしれませんね。
診察は、ご本人が抱えている悩みや困りごと、日々の生活の様子などを把握するとともに、心理検査や場合によっては尿検査や血液検査などを行うことから始まります。心身の症状やその背景について詳しくお話を伺いながら、表情や話しぶりなどを観察し、総合的な観点から診断していきます。治療方法には精神療法やお薬による治療、それらを組み合わせる方法などがあり、患者さんの状態にあわせて、ご本人のご希望も伺いながら、医師が治療方針を検討していきます。また、必要に応じて心理士によるカウンセリングが行われることもあります。
回答者は、
心理士の野口恭子先生です。

野口 恭子(のぐち きょうこ)先生
医療法人和楽会
心療内科・神経科 赤坂クリニック
発達障害を持つ方をパートナーとして選ばれたご家庭をこれまで数多くみてきましたが、家庭生活がうまくいっている方々の多くは、「苦手なこともあるこのパートナーをそのまま受け入れる」ことができているようでした。また、「精神的につらいと感じるなら、この人をパートナーとして選んでいない」という思いが強いです。どのような工夫をするとパートナーをありのまま受け入れることができるようになるか、パートナーが医療機関を受診されているのでしたら、その医療機関で行われている「家族相談」などが大変役に立つと思われます。また、あなた自身がどうしていきたいかについてのご相談であれば、公認心理師や臨床心理士が行っているカウンセリング機関でのご相談をお勧めします。
回答者は、
心理士の廣田瑞穂先生です。
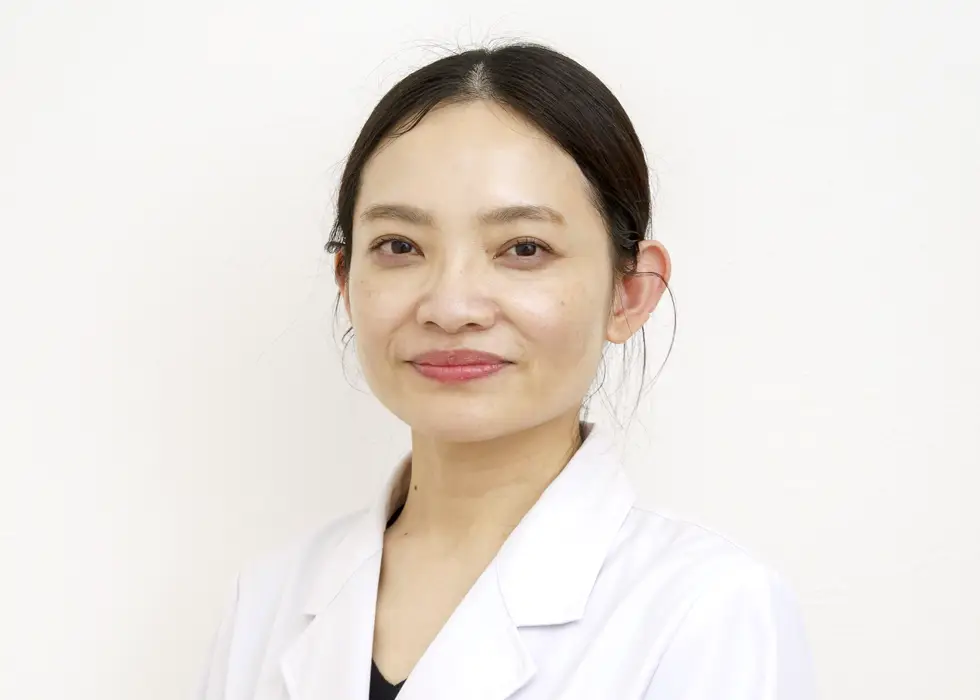
廣田 瑞穂(ひろた みずほ)先生
医療法人悠志会
パークサイドこころの発達クリニック
こころの不調を感じて、受診を検討されているのですね、とても大切な一歩だと思います。最初は皆さん緊張してうまく話せないものですので、どうかご心配なさらずにお越しください。医療機関では、悩みごとや困りごとの内容やその経過について、医師や心理士から、丁寧に質問いたしますので、上手にまとめてお話ししようと考えすぎなくても大丈夫です。必要に応じて、事前にメモを書いてきていただいてもよいですし、ご希望であれば、ご家族が同席することも可能です。
基本的には保険診療で行われますが、医療機関によって多少異なることもあります。また、カウンセリングは自由診療となることもありますので、事前に各医療機関にお問い合わせをいただくとよいかもしれません。
回答者は、
心理士の野口恭子先生です。

野口 恭子(のぐち きょうこ)先生
医療法人和楽会
心療内科・神経科 赤坂クリニック
こころのつらさや不調に
関するお悩み
第一志望の会社に入って精一杯頑張っているご様子が伝わります。そんな中、どうしても出勤できない日があることに戸惑われているようですね。新卒の社会人の方は、職場環境や新しい人間関係など緊張感のある中で業務の達成を求められ、プレッシャーも重なる大変な環境にいます。このように“どうしても出勤できない日がある”のは、仕事の負担やプレッシャーがあなたのキャパシティを超えてしまった可能性があります。ご自身でそのような自覚はありますか?
仕事の負担やプレッシャーがあなたのキャパシティを超えているという問題は、業務の見直しといった工夫が必要です。まずは、自分で仕事を増やしすぎていないか書き出してみましょう。そして、どうしても仕事を減らせない場合は上司やマネージャーに相談してみることをお勧めします。
もし2週間以上続いて出社ができない状態であれば、キャパシティの問題だけではなく、「うつ状態」になっている可能性もありますので、医療機関の受診をお勧めします。受診する際は、職場のメンタルヘルスやリワークを専門とする精神科クリニックなどがよいでしょう。
回答者は、
心理士の廣田瑞穂先生です。
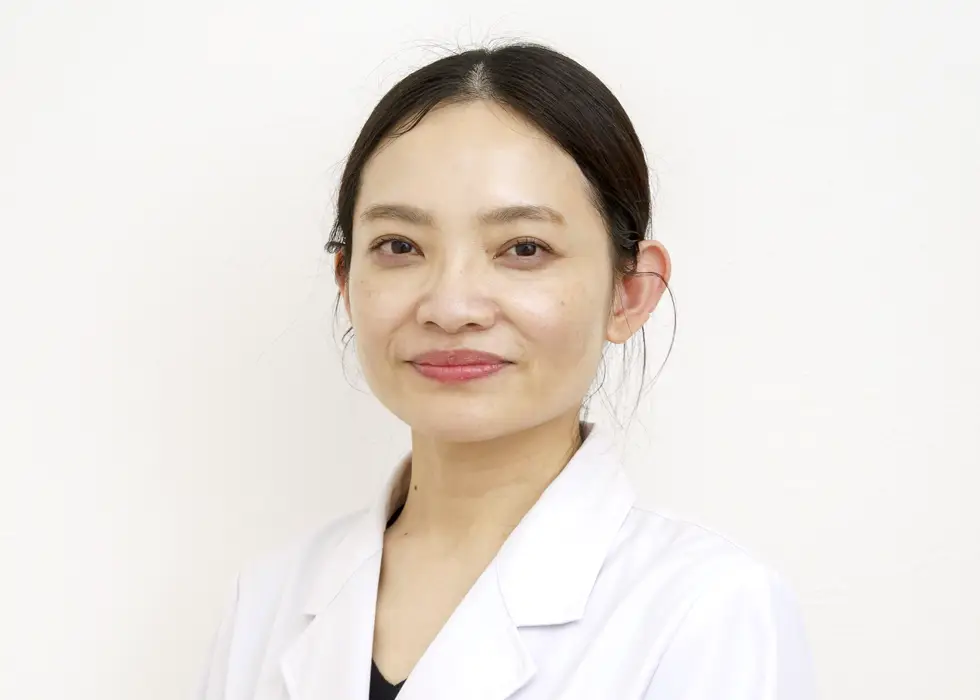
廣田 瑞穂(ひろた みずほ)先生
医療法人悠志会
パークサイドこころの発達クリニック
一般的に、「憂うつな気分の時には大きな決断をしてはならない」ということが原則です。その理由は、このような状態のときは本来とは異なる否定的なものの見方になっていることが多く、その結果、誤った判断をして後悔することがあるからです。
立ち直れないほど厳しく注意されたことで、「思い切って仕事を辞めてしまおうか」と思うほど追い詰められていたのかもしれません。まずは、休養を取ってみることがよいでしょう。そして、今後大きなミスをしないために働き方を見直すことが必要と思われます。
真面目なあなたは1週間も休めないかもしれませんね。あなたの職場に産業医がいるなら、休暇の後に産業医との面談を予約してから、できるだけ1週間程度は休んでみてください。 そういったリフレッシュした頭脳で自分の働き方を考え直すことが今後の健康にも必要なことだと思われます。1週間程度の休暇を取り産業医面談を通して働き方を変えても、不安や憂うつで出社できないことが続くなら、精神科クリニックの受診をお勧めします。
回答者は、
心理士の廣田瑞穂先生です。
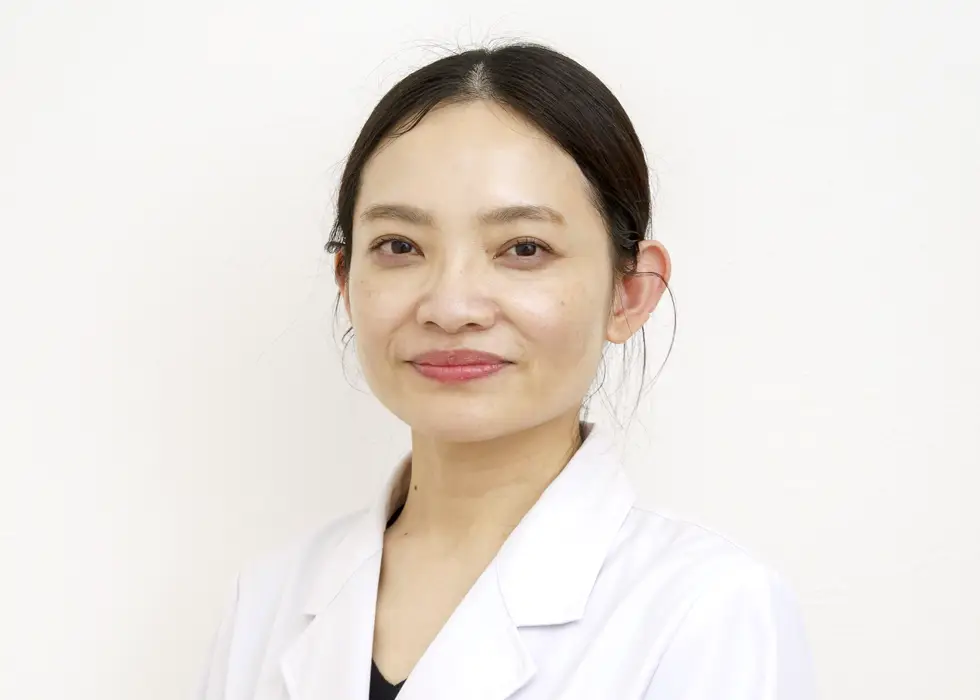
廣田 瑞穂(ひろた みずほ)先生
医療法人悠志会
パークサイドこころの発達クリニック
「こころがつらくなる」ことには、あなたなりの理由や事情があります。それは、誰からも否定される筋合いのものではありませんので、あなたの理由や事情に沿って、「自分はどうしたらよいか」を考えていくことが大切です。
「こころがつらくなる」ことで生活に支障をきたしている場合には、こころが健康的に働かなくなり、「こころの不調」に陥っている可能性があります。わたしたちは、傷ついたり悩んだりして、こころが疲れることが習慣化してしまうと、誰でも自分に自信を持てなくなったり、否定的に考えることが多くなったり、自分のことがよくわからなくなったりしてしまいます。特に、「いつもの自分とは違う」と感じることが増えてきているときには注意が必要です。その状態が続いてしまうと、「こころの不調」が進行してしまう可能性があるからです。
周囲の人から助言されることがあると思います。しかし、自分のことをよく知っている親であったとしても、「こころの不調」に関する知識に乏しい場合には、適切な助言ではない可能性があります。また、良かれと思って言ってくれている言葉であったとしても、その人なりの価値観や気分などさまざまな影響を受けた内容になっているので、参考程度に受け取るのがよいでしょう。さらに、「弱い」「強い」「我慢」という表現は、人によって基準や考えが異なります。このようなあいまいな表現で自分のことを考えてしまうと、さらに自分のことがわからなくなってしまいます。
「こころの不調」を進行させないために、まずはどのような理由や事情で「こころがつらい」状態になるのか、客観的に整理する必要があります。その場合に、医療機関(精神科)への受診が役立つ可能性があります。精神科では、医師や心理士によって、あなたが抱えている「こころの不調」について客観的に整理し、必要な治療や支援を受けることができます。
回答者は、
心理士の広瀬慎一先生です。
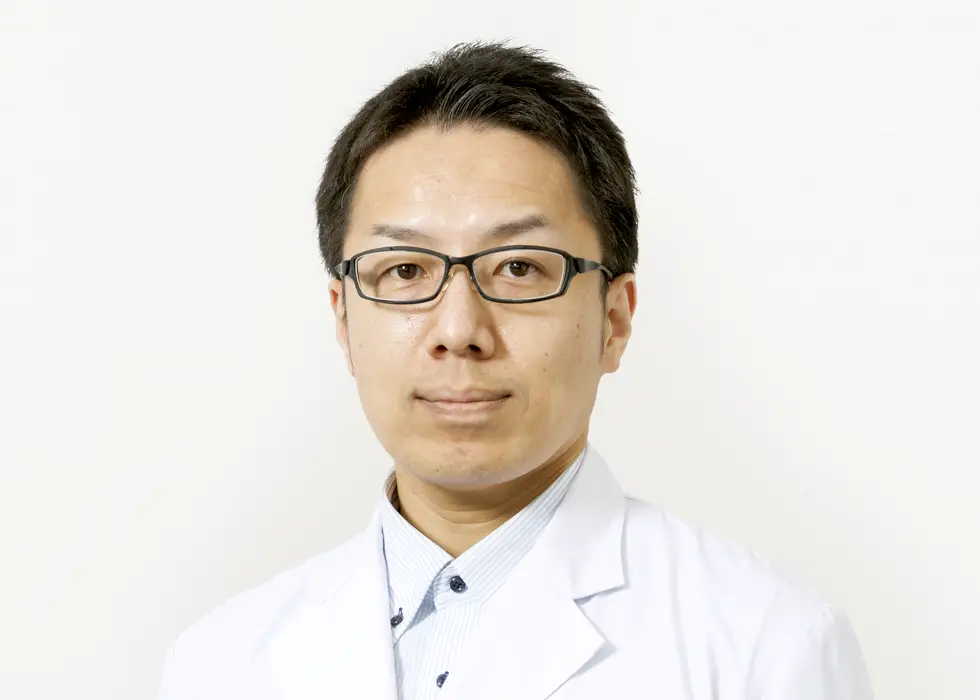
広瀬 慎一(ひろせ しんいち)先生
医療法人社団 五稜会病院
勉強とアルバイトでは要求されることが違います。今やっているアルバイトでは、これまで要求されなかったことをたくさん要求されているのでしょうね。でも、何度も同じミスを繰り返し臨機応変に対応できないことが、くよくよする程度に収まらず、パニックや自己嫌悪にまで発展しているというのは結構深刻な状態かもしれません。そこまでうまくできないのは「今のアルバイトはあなたには向いていない仕事」と考えたほうがよさそうです。そこまで苦労しなくても出来る仕事が世の中にはきっとあるはずです。こうした仕事の得意、不得意における大きな凸凹は「発達特性」として理解されます。就職先を選ぶ際は、大学の学生課や就職支援課の担当の方にアルバイトでの「うまくやれないこと」を説明しながら、就職に向けて相談されることをお勧めします。
回答者は、
心理士の廣田瑞穂先生です。
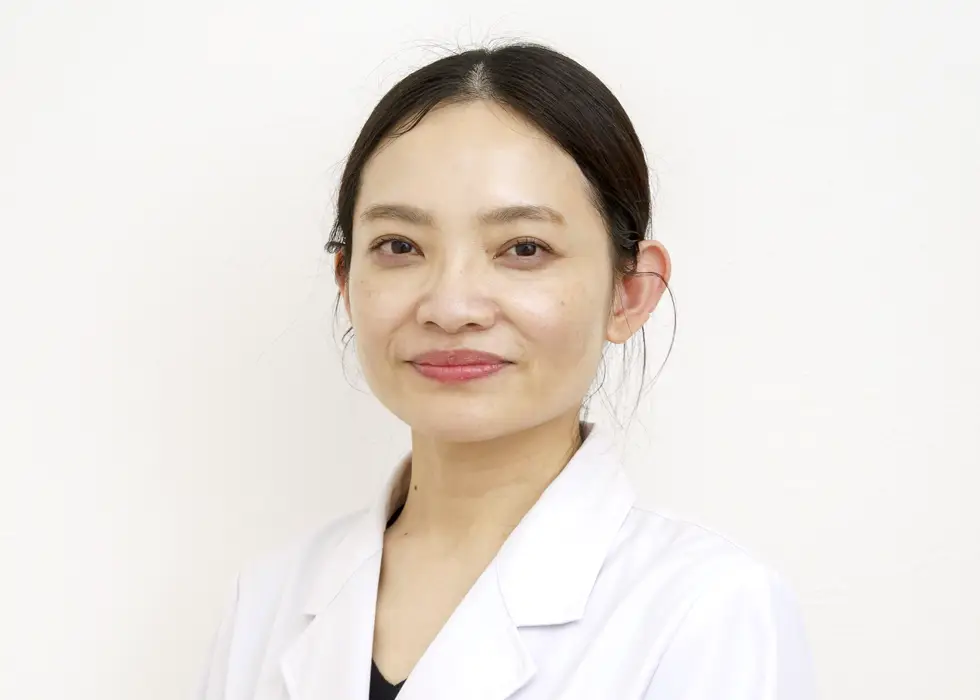
廣田 瑞穂(ひろた みずほ)先生
医療法人悠志会
パークサイドこころの発達クリニック
こころの病気に
関するお悩み
うつ病をはじめとする「こころの病気」は、周囲からはわかりにくいものだと思います。「こころ」の状態は、はっきりと見えるものではないからです。ここでは、うつ病の特徴について、ご説明いたします。
うつ病になると、心身のエネルギーが低下して疲れ切ってしまい、自分の力だけでは立ち直れないくらいの状態となります。そしていつもの生活が送れなくなるほど「こころ」も「からだ」もいうことをきかなくなります。うつ病では、「こころの不調」として、気分の落ち込みや興味・関心がない状態のほか、イライラ、意欲や気力の低下、思考力や集中力の低下、死にたい気持ちなどがあります。「からだの不調」としては、不眠や過眠、食欲の減少や増加、頭痛やめまいなどが多いです。
うつ病は、「自分を責める病気」と言ってよいほど、「自分はダメな人間だ」「自分には生きている価値がない」などと自分を責めて苦しくなってしまいます。周囲に迷惑をかけている感覚も強くなるため、さらに自分を自分で追い詰めてしまう思考パターンに陥ってしまいます。うつ病になると判断力が落ちて、自分の限界を自覚できなくなります。特に、「まだ頑張れる」「まだ大丈夫」と言っている場合には、うつ病のサインと考えてもよいかもしれません。
うつ病の治療は、心身のエネルギーが低下した状態に対して、十分に休息を図れるように環境を整えるところから始まります。そのため、長い時間がかかることもありますので、治療は焦らず、ゆっくりと進めることが大切です。うつ病の症状が回復しても、心身のエネルギーが低下するようなストレスの多い生活をしたり、つい無理をしてしまったりすることで、うつ病を再発させてしまうこともあります。このような再発を防ぐためにも、自分のうつ病の特徴を知り、心身のエネルギーを低下させない生活の仕方を身につけていく必要があります。
回答者は、
心理士の広瀬慎一先生です。
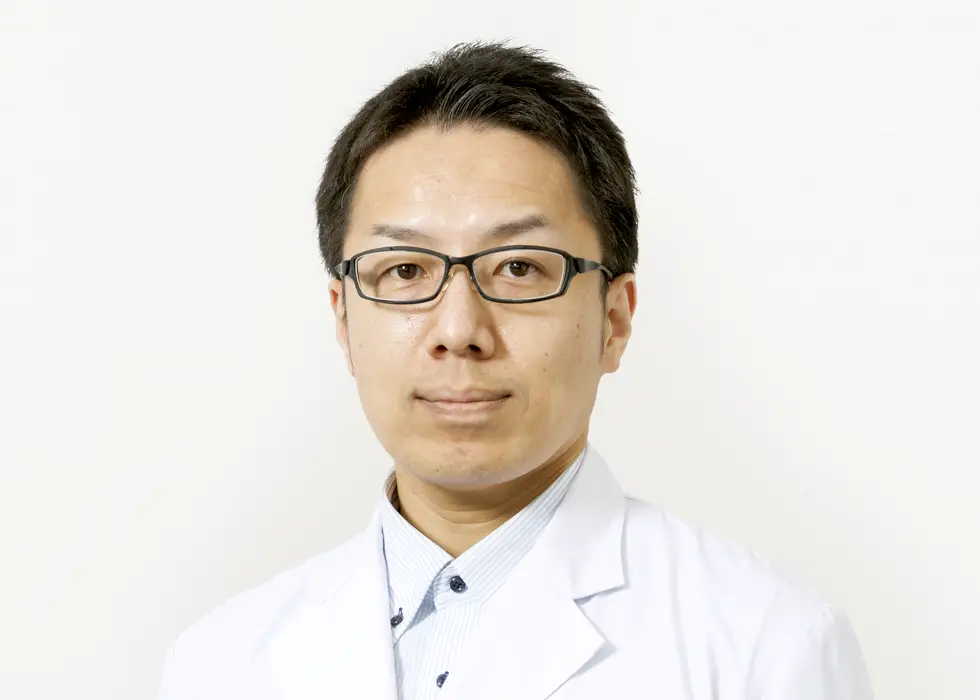
広瀬 慎一(ひろせ しんいち)先生
医療法人社団 五稜会病院
娘さんがひどく落ち込んで出社できなくなってしまっているとは、とても心配ですね。うつ病の患者さんには、生真面目な人が多い傾向はありますが、「楽観的だから大丈夫、生真面目だからうつ病になる」とは限りません。
うつ病は、脳内の神経伝達物質が関連していると言われています。さまざまなストレスを受け続けることによって、考え方や行動パターンなども変化が生じるため、もともとの性格やこころの強さ・弱さとはあまり関係ないかもしれません。結婚や出産、昇進や転居など、はたから見ると幸せだと思えるようなイベントも、大きなストレスになることがあると言われています。うつ病のきっかけは、人それぞれにいろいろあります。
うつ病は、誰にでも起こり得る、実はとても身近なこころの病なのです。
回答者は、
心理士の野口恭子先生です。

野口 恭子(のぐち きょうこ)先生
医療法人和楽会
心療内科・神経科 赤坂クリニック
こころの病気の治療に
関するお悩み
服用に関しての疑問、不安を解消することは、治療を受けるうえでとても大切なことです。疑問や不安について主治医に確認するのは、患者さんの権利でもありますので、遠慮なく質問してみるとよいでしょう。
そのうえで、「こころの病気」と「薬」との関係についてご説明いたします。医師は、患者さんの状態に応じて適切な治療法を選択していますので、医師の指示どおりに、十分な量、十分な期間、服用を続けることが必要とされています。治療の途中で、勝手に減らしたり、服用をやめてしまったりすると、症状が改善しないまま慢性化してしまう可能性もあります。もちろん、治療に関する不安や希望を伝えることは、医師と患者さんがコミュニケーションを図りながら、必要な情報を共有し、患者さんの想いや希望に沿って共に治療方針を決めるために重要なことです。
服用期間について一概に述べることは難しく、病状、薬の種類、目的などによって大きく異なります。また、一般的に、症状はいったん改善がみられてもぶり返すことがあります。良くなったり悪くなったりという波を繰り返しながら回復に向かっていくため、良くなったと感じてもしばらくの間は服用を続けることが多いです。
「こころの病気」において薬による治療は、症状の改善だけでなく、再発を予防する目的でも使用されます。回復の過程は、人それぞれ異なるため、一概に当てはめることは難しいことですが、一般的に「急性期」「回復期」「再発予防期」の3つの段階で考えられます。「急性期」は、治療の初期で、症状が強く現れている時期であり、症状を取り除くために服用します。「回復期」は、症状が落ち着いてきた時期であり、症状の安定を維持するために服用します。「再発予防期」は、症状が良くなり、生活への支障もない時期です。この時期は再発を予防するために服用を続けたり、徐々に減薬したりすることがあります。症状が良くなったときには「薬を飲まなくてもいいかな?」「治ったのに何で飲むのかな?」と思うことがあるかもしれません。しかし、再発のリスクを高めないためには、医師の指示に従って服用を続けることが大切です。
なお、「こころの病気」の治療は、薬だけでなく、病気に関する知識を身につけたり、関連する問題の解決策や対応策などを医師や心理士と話し合いながら身につけていくことも重要です。
回答者は、
心理士の広瀬慎一先生です。
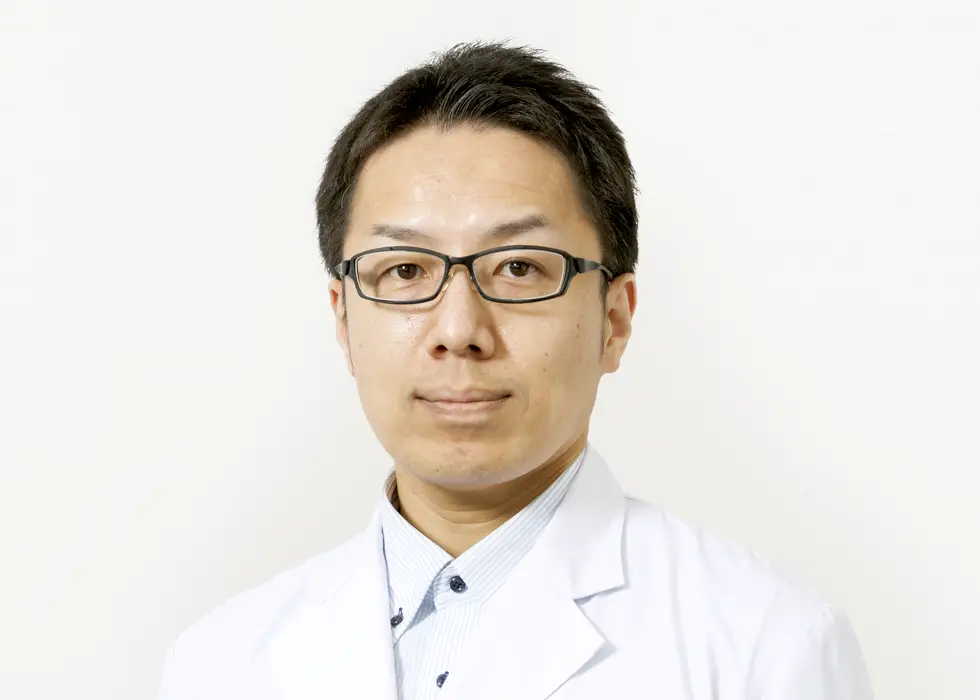
広瀬 慎一(ひろせ しんいち)先生
医療法人社団 五稜会病院
お薬が続いていることに不安を感じていらっしゃるのですね。カウンセリングを受けたいことや服薬を継続することに不安を感じていることも含め、主治医の先生によくご相談されるとよいと思います。医療機関では、患者さんに寄り添い、希望を伺いながら治療方針を決定していきますので、ご本人の不安な気持ちも大切な話題です。
主治医の先生にお気持ちをお話しいただいたうえで、服薬の効果や今後の治療方針、薬を続けることや中止することのメリット・デメリットをよく確認してみるのはいかがでしょうか。医療機関でのカウンセリングは原則として医師の治療方針に則って行われます。症状や状態によっては、お薬とカウンセリングを組み合わせて行なう方が、治療効果が高いこともあります。
いずれにしても、減薬のタイミングなどを自己判断せずに、主治医の先生とよく相談して、安心して治療を続けられることが大切だと思います。
回答者は、
心理士の野口恭子先生です。

野口 恭子(のぐち きょうこ)先生
医療法人和楽会
心療内科・神経科 赤坂クリニック
症状がだいぶ良くなってきたと感じられていることは、治療がうまく進んでいる証拠です。大変な中でしっかり服薬を継続され、生活の工夫などをして過ごされてきた結果だと思います。症状もよくなったしお薬なしでの生活に早く戻りたいというお気持ちなのですね。
例えば風邪や発熱では、咳が出なくなる、熱が下がるなど症状がなくなったら飲むのをやめるお薬もありますので、お薬に対しては、多くの人がそのような印象を持っているのではないかと思います。ですが、精神的な病気の場合、症状によっては治療期間が長くなります。「ウイルスが原因の風邪」のように原因が特定しづらいため、再発を防ぐためにも、症状がなくなってからも服薬を続け、ある程度その状態を維持できたら、お薬を少しずつ減らしていくのが一般的な治療法です。
自己判断でお薬をやめてしまうと、再発したり慢性化してしまったりするリスクが高まると考えられています。まずは、お薬なしでの生活に戻りたいという気持ちを主治医の先生にお伝えしてみてください。どのような理由で様子を見た方がよいと考えておられるのかをお伺いできると思います。また、現在のよくなった状態がどれくらい続いたらお薬をやめられるのかもお尋ねになってみると、見通しが立って安心感につながると思います。
回答者は、
心理士の廣田瑞穂先生です。
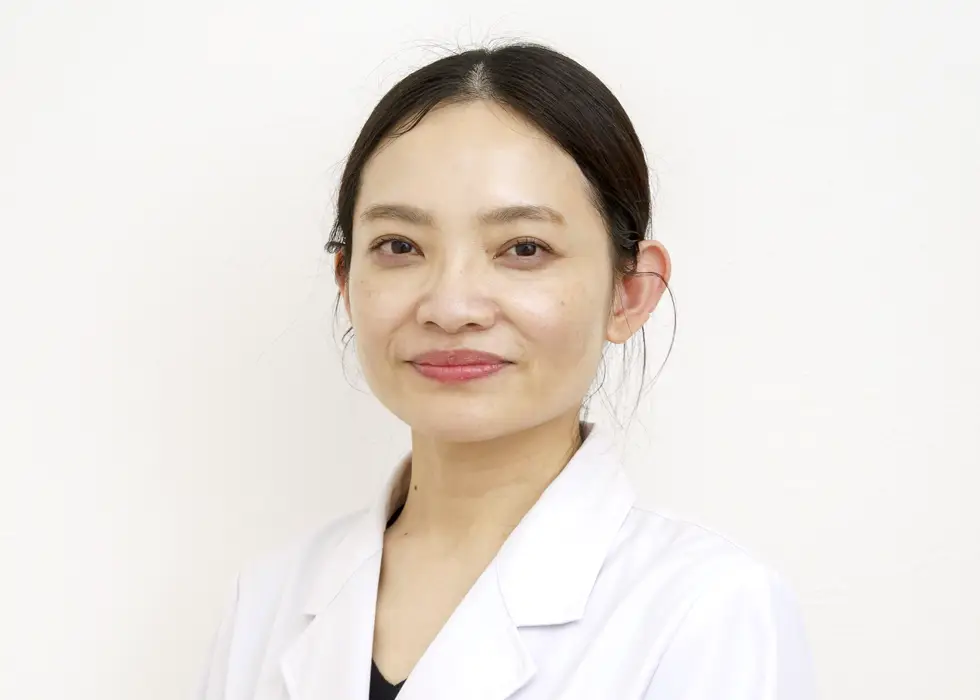
廣田 瑞穂(ひろた みずほ)先生
医療法人悠志会
パークサイドこころの発達クリニック
「今後、働けなくなったらどうしよう」という心配は、当然のことだと思います。現実的な問題であり、経済的サポートに関する知識や情報が力になることでしょう。うつ病で働くことができなくなった場合には、さまざまな経済的サポートを利用することができます。そのようなサポートを受けながら、経済的に安心してうつ病の治療や休養に専念することができるのは、とても大切なことです。ここでは、主要なものをいくつかご紹介いたします。
「傷病手当金」は、病気やケガのために仕事を休む場合に、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。3日間連続して会社を休み、さらに4日目以降休んだ場合、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。なお、国民健康保険には傷病手当金の制度はありません。
「障害年金」は、病気やケガによって日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、年金加入者が受給できる年金です。
「自立支援医療制度」は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。うつ病も対象となります。通常、医療保険による医療費の自己負担額は「3割」ですが、自立支援医療制度を利用すれば「1割」まで軽減することができます。ただし、世帯の総所得額によっては対象外となる場合があります。
「失業保険(失業手当)」は、うつ病に限らず、失業した人が就職するまでの一定期間、受給できる給付金のことです。具体的な受給期間や金額は、その人の状況によって異なります。
詳細は、勤務先、市区町村の相談窓口、ハローワーク、年金事務所、医療機関の精神保健福祉士などに相談するとよいでしょう。
回答者は、
心理士の広瀬慎一先生です。
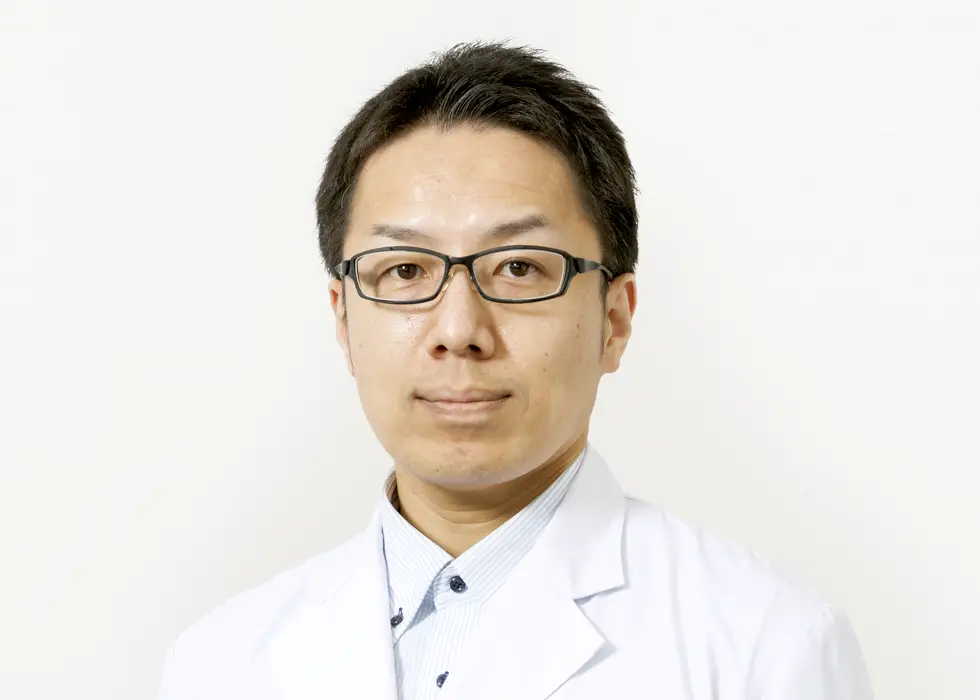
広瀬 慎一(ひろせ しんいち)先生
医療法人社団 五稜会病院
ひとりで悩みを抱え込まないで ~こころの専門家に会いに行こう~

坂野 雄二(さかの ゆうじ)先生
医療法人社団 五稜会病院
札幌CBT&EAPセンター長/心理室顧問
「こころが疲れる」とは
こころが疲れるというのは決して特別なことでも、「変な出来事」でもありません。誰にでも起こりうる、とても身近な問題です。そのきっかけには、「ストレス」が大きく関わっています。現代社会はストレス社会とも言われており、私たちの身の回りには、ストレスの原因となる出来事がたくさんあります。たとえば、仕事の負担や生活していく上でのさまざまな問題(職場環境、子育てや教育、人間関係など)があてはまりますし、暑さ・寒さといった物理的な生活環境もストレスの原因になります。ストレスを受け続けると、こころや身体が対応しきれなくなって不調をきたすことがあります。このようなとき、私たちのこころは疲れるのかもしれません。
「こころの疲れ」に気づくサイン
こころの疲れには、次の3つの段階があります。自分のこころの状態に気づくことが、適切な対処方法をみつける第一歩です。
①イライラする、ソワソワする
最初にあらわれるサインは、何となくイライラする、ソワソワして落ち着かない、怒りっぽくなるなどのこころの変調です。作業効率が下がる、人前に出たくないといった、行動の変化がみられることもあります。イライラやソワソワなどは、自分で気づきやすいサインですが、周囲の人が気づく場合もあります 。
②気持ちの落ち込み、不安から抜け出せない
次にあらわれるサインは、気持ちの落ち込みや不安です。こうした感情が起こっても自分でコントロールできるようなら、こころはまだ健康な状態にあるといえます。
③病的な変化があらわれる
問題なのは、落ち込みや不安が強くて自分ではコントロールできず、①や②の状態から抜け出すことができなくなることです。気持ちがずっと沈んだままの場合や、外に出られない日々が続く場合、こうした変化によって生活に支障が出てしまうような場合は、「精神機能の問題」が起こっていることが考えられます。このとき、不安症やうつ病、適応障害といったこころの病気が隠れているかもしれません。
人間関係や仕事などの心理社会的ストレスは、血圧をあげたり消化器の症状を引き起こしたりといった、からだの症状を引き起こすことも知られています。こうした病気は「心身症」と呼ばれています1)。精神機能の問題も心身症も、自分だけで対処することは困難なので、こころの専門家のいる病院できちんと治療を受けることが大切です。
こころが疲れてしまう前に

イライラや不安は、一時的なものであれば自分でコントロールできます。私たちは普段から感情をコントロールしており、たとえば嫌なことがあったときには、仲間と楽しくお酒を飲んだり、自然の中を散歩したり、音楽を聴いたりすると、気分がスッキリするという経験は誰もがしているはずです。そうした経験を振り返って、イライラや不安を感じたときの自分なりの対処法を知っておくとよいでしょう。
しかし、自分でコントロールできない段階まで進んでしまったら、ひとりで抱え込まず、こころの専門家の力を借りてみてはいかがでしょうか。
こころの専門家に相談してみよう
こころの専門家というと、まず病院の「精神科」や「心療内科」が思い浮かぶかもしれません。精神科はこころの病気(精神疾患)を専門に診るところ、心療内科は心身症を専門に診るところ、という違いはありますが、こころの専門家に相談してみようと思ったときは、まずはどちらの診療科であっても相談してみることをお勧めします(「精神科・心療内科」と両方の診療科を掲げている病院やクリニックがあれば、最初に相談するにはよいかもしれませんね)。不安がとても強い人、落ち込みが強い人、気分の変動が激しい人などは精神機能の問題を抱えている可能性があるので、精神科の受診が望ましいかもしれませんが、心療内科を受診しても、必要に応じて適切な専門家を紹介してくれます。
こころの専門家が見つからない場合は、普段お世話になっている内科や婦人科などのかかりつけ医に相談してみるのも1つの方法です。あるいは職場の産業医に相談してもよいでしょう。産業医は症状などから判断し、必要に応じて適切な病院や診療科を紹介してくれるはずです。
身近なこころの専門家「心理士」
こころの専門家は、精神科医・心療内科医だけではありません。心理学にもとづいた知識や技術を活かして、こころの問題に取り組む「心理士」も身近な頼れる存在です。
近年、社会的にこころの問題が大きな課題となり、心理士への期待が高まっています。心理士は、病院においては医師や看護師などとチームを組んでこころの治療に取り組んでいますが、それ以外にも教育施設(子どもや保護者の教育相談など)、矯正施設や刑務所などの司法施設(少年や受刑者への心理指導など)、福祉施設(高齢者や児童などの相談や支援)、一般企業(社員のメンタルヘルス維持・増進など)など、さまざまな領域で活躍しています。

こうした心理士の重要性をふまえ、「公認心理師」という国家資格が2017年に誕生しました。公認心理師は、大学・大学院等で所定のカリキュラムを履修し、国家試験に合格した人に与えられる資格で2)、2024年6月末現在で約73,000人が資格を有しています3)。
なお、心理に関する資格として、「臨床心理士」や「産業カウンセラー」などもあります。これらは国家資格とは異なり、民間団体が認定している資格です。いずれも古い歴史があり、団体が定める試験に合格することで資格を有することができます。
-
※
以降、本記事中の「心理士」という記載は「公認心理師」を指します。
病院で出会う心理士の役割
こころの診察や治療は、精神科医や心療内科医が中心となって行いますが、心理士も心理面から患者さんと深く関わります。
①予診
初めて受診した患者さんには、医師が診察を行う前に、予備的な問診(予診)を受けていただきます。こころに関する予診は心理士や精神保健福祉士などが行う場合が多く、こころや身体の状態、抱えている悩み、生活環境などをじっくりお聞きします。予診は、患者さんがこころを落ち着けて相談できる時間ですし、医師が診察をスムーズに行うための情報源でもあります。
②心理検査
医師による診察の後は、必要な検査を受けていただきます。心理検査は、医師の指示を受けて心理士が実施します。患者さんの症状の心理社会的背景などを分析したり、患者さんの性格特性や生活状況を把握したりして、その結果を医師に報告します。
③心理療法・カウンセリング
診断が確定して治療方針が決まったら、治療を開始します。心理療法やカウンセリングは医師や心理士が行います。心理療法・カウンセリングでは、まず患者さんの話を傾聴します。そして患者さんのありのままの状況を受け止め、患者さんとコミュニケーションをとっていく中で、患者さん自身に「自分には苦難から抜け出して、新しい自分を作り上げる力があるのだ」と気づいてもらえるようにします。大切なのは患者さん自身がそのことに気づくことなので、心理士が積極的に指示を出したり、誘導したりすることはありません。
心理士の役割を例えるなら、荒野を切り拓いて線路を敷くときに、下草を刈って周囲を見通せるようにすることです。どのように線路を敷き、どう走っていくかは、話し合いのなかで患者さん自身に見つけてもらいます。心理士は、患者さんが自らの力で進んでいく方法をみつけて自立していくまで、一緒に取り組んでくれる心強い存在なのです。
医師と心理士は、こころの治療にあたる「車の両輪」
病院で心理士が心理療法を行うときは、医師の指示を受け、医師と情報共有しながら進めていきます。つまり、医師と心理士は車の両輪のように協力しながら、こころの治療にあたっているのです。「診察は不要で、カウンセリングだけ受けたい」という患者さんもいらっしゃいますが、カウンセリングは医師による診察と指導をセットで行うことが大切だということを、理解していただく必要があると思います。
患者さんのこころをチームで支える

こころの診療や治療を行うときは、医師と心理士のほかにも、さまざまな専門職のスタッフが患者さんを支えています。看護師は患者さんの身体とこころのケアを、作業療法士は社会復帰や日常生活のためのリハビリを、栄養士は入院中の栄養管理を、薬剤師は薬剤の服薬管理・指導を、精神保健福祉士は退院後の生活や公的支援の相談などを行います。
このように病院では、さまざまなスタッフがチームとして患者さんのこころを守ります。こころが疲れてしまったときは、ひとりで悩まず、病院の受診を検討してみるとよいでしょう。
こころのホームドクター・ホームカウンセラーを身近に
最近は、身体の不調を感じたときにまず相談する「ホームドクター(かかりつけ医)」をもつ人が増えてきました。かかりつけ医の多くは、内科など主に身体疾患を診ている診療科だと思いますが、かかりつけ医の1つとして精神科や心療内科をもつのもよいのではないかと思います。イライラした気分が自分では抑えられないとき、気軽に相談できる精神科や心療内科の医師や心理士がそばにいると、直接サポートを受けることができるだけでなく、サポートしてくれる味方がいるというだけでとても心強いことでしょう。すべての精神科・心療内科に心理士がいるわけではありませんが、いつでも相談できるこころのホームドクターとホームカウンセラーを見つけてみてはいかがでしょうか。
出典
-
1)
日本心身医学会ホームページ https://shinshin-igaku.com/about/about/
-
2)
公認心理師法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80ab4905&d
-
3)
2024年度 公認心理師の都道府県別登録者数 https://www.jccpp.or.jp/download/pdf/number_of_registered.pdf



 の相談
の相談
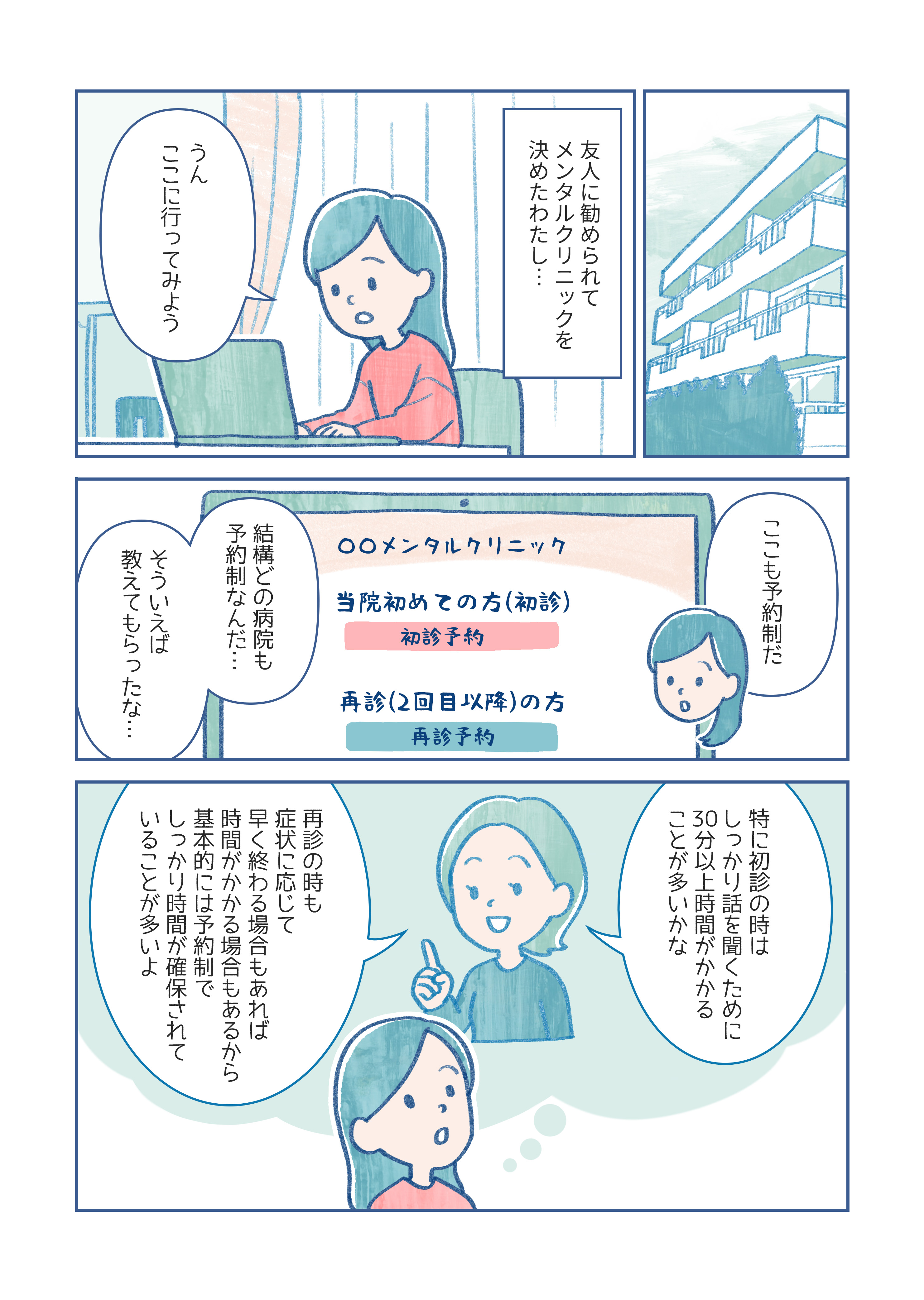
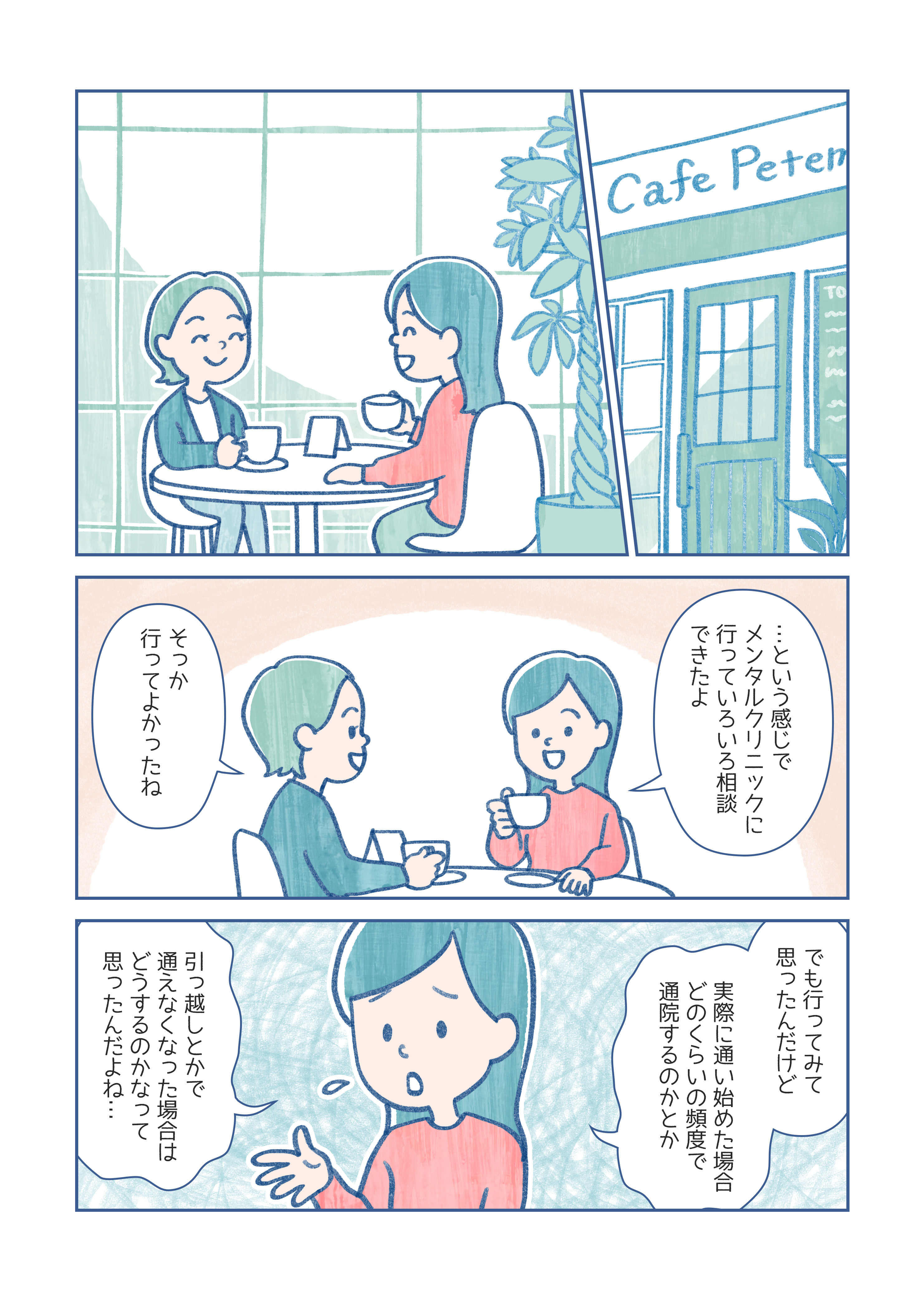
 病院検索
病院検索